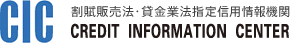沿革
- 1983年
- 7月
- 通商産業省(現:経済産業省)の「消費者信用産業懇談会」が販売信用分野における信用情報機関の整備統合を提言
通商産業省が(社)日本割賦協会(現:(一社)日本クレジット協会)の信用情報交換所と(株)日本信用情報センターとの統合について話合いを開始するよう要請
- 11月
- (社)日本割賦協会、(株)日本信用情報センターに(社)全国信販協会を加えた三者が、信用情報機関を一本化することに合意
- 1984年
- 9月
- (株)信用情報センター(現:(株)シー・アイ・シー)創立
- 1985年
- 4月
- 営業開始、信用情報サービス開始
- 1986年
- 3月
- 情報処理を(株)流通情報システムサービス(現:(株)シーアイシーシステムズ)に専属委託
- 6月
- 信用情報の開示受付を開始
- 1987年
- 3月
- CRINサービスを開始
- 1988年
- 9月
- 照会の全面オンライン化
- 1989年
- 9月
- 本社を新宿区新宿5-15-5(新宿三光町ビル)に移転
- 1990年
- 6月
- 資本金を3億6,000万円に増資
- 1991年
- 8月
- 「株式会社シー・アイ・シー」に社名を変更
- 1992年
- 6月
- 資本金を4億8,000万に増資
- 7月
- 自社ホストマシンによるCICシステムセンターを稼働
- 12月
- (株)流通情報システムサービスの社名を「株式会社シーアイシーシステムズ」に変更
- 1993年
- 3月
- (株)シーアイシーシステムズがCICロック(登録データ暗号化ソフト)を開発
- 12月
- CICシステムセンターが通商産業省の「情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施事業所認定」を取得
- 1994年
- 5月
- 加盟会員により構成される業務委員会を設置
- 1995年
- 10月
- 信用情報の保有件数が1億件を超える
- 1996年
- 3月
- インターネットにホームページを開設
- 4月
- 加盟会員により構成される「地区協議会」を全国12地区に設置
- 10月
- バックアップセンターを開設
- 1998年
- 1月
- 新経営理念を制定
セキュリティ推進部署として業務検査部(現:内部監査部)を設置
- 1999年
- 4月
- 業務運営規則・業務運営細則を施行
- 2001年
- 3月
- (社)日本クレジット産業協会(現:(一社)日本クレジット協会)・(社)全国信販協会・CICの三者で
「クレジット産業における個人信用情報保護・利用に関する自主ルール」を制定、同時に自主ルール運営協議会を設置
- 2002年
- 2月
- 信用情報の保有件数が2億件を超える
- 7月
- 資本金を5億円に増資
- 8月
- ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得(CICシステムセンター)
- 2003年
- 3月
- CPU接続による信用情報照会ネットワークをIP化
信用情報の保有件数が3億件を超える
- 2004年
- 3月
- 本社を新宿区西新宿1-23-7(新宿ファーストウエスト)に移転
- 2005年
- 4月
- 認定個人情報保護団体 クレジット個人情報保護推進協議会(現:(一社)日本クレジット協会)を設立
(自主ルール運営協議会を改組)
- 5月
- 信用情報の保有件数が4億件を超える
- 2006年
- 9月
- オープン技術基盤採用による新基幹システムを稼働
- 2008年
- 10月
- 貸金業法に対応した登録システムを稼働し、情報の登録受付を開始
- 2009年
- 2月
- 貸金業法に対応した照会システムを稼働
- 3月
- 信用情報の保有件数が5億件を超える
- 2010年
- 1月
- 割賦販売法に対応した登録システムを稼働し、情報の登録受付を開始
- 3月
- 貸金業法に基づく「指定信用情報機関」として内閣総理大臣から指定を受ける
FINEサービスを開始
割賦販売法に対応した照会システムを稼働
- 7月
- 割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」として経済産業大臣から指定を受ける
- 2011年
- 4月
- 「インターネット開示」を開始
外部の有識者により構成される「内部統制専門委員会」を設置
- 7月
- 郵送開示業務を首都圏開示相談室(現:郵送開示センター)に一元化
- 2012年
- 2月
- JIS Q 15001(プライバシーマーク)の認証を取得
- 3月
- コールセンターを開設
- 11月
- 信用情報の保有件数が6億件を超える
- 2013年
- 4月
- (株)シーアイシーシステムズに委託していたシステム開発・運用業務を譲り受け、当社に移管
- 2014年
- 1月
- 名寄せ処理方式を変更した「新信用情報データベース」を稼働
- 2015年
- 4月
- スマートフォンによる「インターネット開示」を開始
- 11月
- 信用情報の保有件数が7億件を超える
- 2019年
- 3月
- 「本人申告制度」のインターネット対応を開始
- 2021年
- 4月
- 信用情報の保有件数が8億件を超える
- 12月
- 照会・登録手段APIシステムを稼働
- 2022年
- 5月
- IDEAサービスを開始
- 2023年
- 1月
- 経済産業省が定める「DX認定事業者」の認定を取得
- 11月
- クラウドセキュリティに関する国際規格ISO/IEC27017の認証を取得
- 2024年
- 11月
- 消費者への「クレジット・ガイダンス」の提供を開始
- 2025年
- 4月
- 加盟会員への「クレジット・ガイダンス」の提供を開始